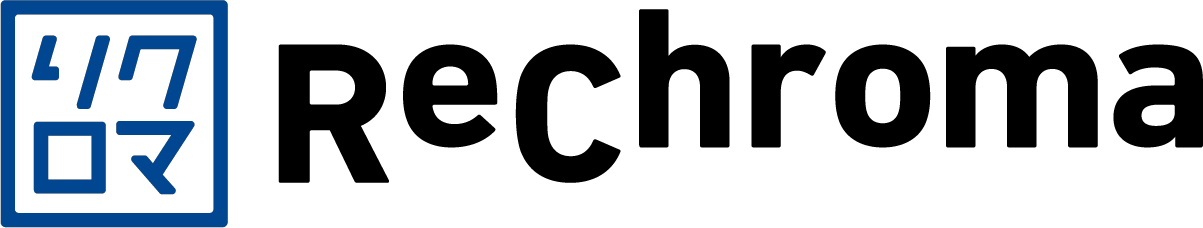Last Updated on 2025年4月11日 by Moe Yamazaki
プロジェクト背景と経緯
御社では、これまで気候変動対策について、どのような取り組みをされていましたか?
山田様: 以前よりScope1とScope2についての取り組みを既に進めており、ここ最近の世間の状況やお客様からのご要求からScope3を含めた対応が必要になってきおりました。弊社としても、今後早期に取り組まなければならないことは認識しており、取り組むなら速やかに導入したいという思いがありました。
その中で、改めて今回CFPの対応について取り組まれた経緯とどんな背景があったかお伺いしてよろしいでしょうか。
山田様: 弊社は自転車用部品を取り扱っております。弊社の商品は、日本に限らず海外の自転車向けにも販売しているため、我々が納入する完成車メーカー様などからも、既にご要求を、頂いておりました。また、我々が、海外市場で事業を行う上で、CFP算定などの対応は必要不可欠だろうということで、対応を検討しておりました。
福田様: 弊社は「安全、健康、環境に新しい価値を創造し、社会に貢献します」という企業理念の下、自転車用安全部品を製造販売していますが、安全だけでなく環境にも配慮した製品を作るという考えがあります。カーボンフットプリントを算定できるようになり、我々の生産活動ではどれぐらいGHGを排出しているのかを把握することは必要だろうということで取り組みました。
CFPの要請は、現状ではやはり海外からの要請が多いのでしょうか。また、その海外とのやり取りで大変だった点や、現状で課題だと考えているところはございますか?
山田様: はい。数年前に、お客様より「一覧表へ、CFP算定結果を記入してください」という問い合わせをいただきました。CFPという言葉、どういった数値を答えるべきか、分かっていても、実際にどう対応すればよいのか全く分からない状態でした。
問い合わせを受けて初めてCFPという概念に触れ、一からキャッチアップされていったのでしょうか?それとも、もともと認識はされていましたか?
福田様: 私は全く認識していませんでした。ネット情報でCFP算定の存在は知っていましたが、「実際どうやって算出するのか」が分からず、山田が事前に調査していたため相談し、「本格的に取り組む必要がある」という結論に至りました。弊社内では専門知識を持った人材がいなかったため、手探り状態でセミナーに参加したり、問い合わせをしたりする中で、リクロマ様と接点を持つことができ、今回の取り組みに至りました。
最初はセミナーを受講するなど、かなり手探り状態のところから私どものリクロマを選んでいただいたかと思いますが、最終的に我々を選んでいただいた理由や背景をお伺いしてもよろしいですか?
山田様: 一般的にコンサルティングでは、質問の内容・回数・時間が制限されることが多いのですが、リクロマ様にはそういった制約がなかったことが大きなポイントでした。また、他社様のご提案にはソフトウェアがセットになっていることが多く、確かにメリットとして算定は容易になりますが、弊社の事業規模を考えると、継続的な費用負担は避けたいと考えていました。自社製品の特性から「独自でも対応できるはず」と考え、外部ソフトに依存せず自社完結できるパートナーを探した結果、選択肢はそれほど多くありませんでした。
御社の代表者様は様々なセミナーを開催されており、情報収集がしやすかったのも選定理由の一つです。様々なセミナーを比較検討し、他社や行政主催のものも含めて参加する中で、リクロマ様を選ばせていただきました。

実施体制と進行状況
今回のCFP算定対応にあたって、御社内ではどのような体制で取り組まれましたか?
山田様: 社内でプロジェクトを立ち上げ、品質保証部と算定対象工場が連携する形で進めました。将来的には全社的に取り組む必要があるという前提でメンバーを選抜し、事務局として2名が担当する体制で取り組みました。
社内連携をする中で難しかった点や逆にスムーズに進められた点について教えていただけますか?
福田様: ライフサイクルフロー作成時に、調達経路がケースバイケースで変わることが課題でした。今回は1つの事例に絞って算定に取り組みましたが、別の担当者でも類似モデルについて同時に検証していました。例えば、「資材調達経路が変わった場合のGHG排出量への影響」などです。
リクロマ様のコンサルティング資料は、いわば「線路」が敷かれているような印象で、作業が脱線せずに進められました。ある程度の選択肢が示されていたので、枠組みの中で作業を進めることができ、結果的にはそれほど大変だという印象はありませんでした。
改善点や課題に感じられた部分はありましたでしょうか?
山田様: 最初の算定に着手する段階で基礎知識が不足していたため、細部においてどう判断すべきか迷うことがありました。特に「どの係数を選ぶべきか」という点が最大の課題でした。
福田様: 確かに「係数選定の根拠」や「なぜこの値を使うのか」という理論的背景については、まだ十分に理解できていない部分があります。ただ「算定を実施する」という当初の目的は達成できたので、今後は実務を通じてさらに理解を深めていきたいと考えています。そういった背景についてももう少し詳しいご説明があると、より理解が進んだかもしれません。
CFP算定に取り組む前の想定と、実際に取り組んでみての印象に違いはありましたか?
山田様: それほど大きなギャップはありませんでした。算定の際の係数選定や計算方法が最も難しい部分だと考えていましたが、リクロマ様とのやり取りを通じて、フォーマット化された枠組みの中で作業できたことが大きな助けになりました。係数が変わる場合の対応方法なども示していただけたので、一から全てを行う大変さを感じなかったことは大きな収穫でした。実際には複雑な作業のはずなのですが、現在は新製品の検証も自分で計算できるようになっています。
福田様: 当初は算定結果がどのように出てくるのか想像すらできませんでしたが、実際に手順を教えていただいたことで、明確なイメージを持てるようになりました。
現状と今後の展望
現在は商材の拡充を進められているとお聞きしていますが、どの程度まで広げられていて、何か課題はありますか?
福田様: 現在は自転車用反射板の算定を進めています。年末から今年にかけてスタートし、3月末までに2モデルの算定完了を目標にしています。既に1モデルがほぼ完了し、残りの1モデルも3月末までに仕上げる予定で順調に進んでいます。
先ほどの、調達経路が変わる商材についてはどういった対応を進められているのでしょうか?
福田様: 社内生産と外注生産の比較や、国内調達と海外調達の材料の比較などが挙げられます。海外調達の方がGHG排出量は多くなると予想されますが、具体的にどの程度増加するのかを数値で把握することに取り組んでいます。単なる算定だけでなく、排出量の数値的な理解を深めることを目指しています。
今後、商材展開に加えて、CFPに限らずCO2削減などの対応も検討されていると思いますが、どのような計画をお持ちですか?
山田様: 削減についてはCO2以外にも様々な観点があります。例えばヨーロッパでは、期限と数値目標が法規制で設定され、削減に取り組むことが求められています。弊社はSBT認証を基に削減努力を進めておりますが、さらなる取り組みが必要であると考えています。
現在はリフレクターのCFP算定を行っていますが、今後は自転車用ライトなど他の商品にも対応を広げていく必要があります。また、リサイクル材や再生材の取り扱いは大きな課題になってくると想定しています。特に、供給者からのCFP数値が入手できない場合の対応は一つの重要な問題です。
データ収集プロセスについて、他社では必要なデータの取得が難しいケースが多いのですが、御社ではいかがでしたか?
福田様:当初はサプライヤーへの問い合わせがもっと多くなると予想していましたが、実際には社内で既に把握していたデータを活用できることが分かり、それほど苦労はありませんでした。生産総量の把握のために社内データシステムを一部修正するといった工夫は必要でしたが、基本的に必要なデータは社内に存在していたため、データベースの処理、加工方法の改良を行いました。
山田様:今回コンサルティングいただいた製品は基本的に国内輸送で完結していますが、海外からの輸入が対象になった場合のCFP算定については、まだ実践経験がなく、実際に取り組んでみないと分からない部分があります。

今後の課題と計画
今後「配分データ」から「積み上げデータ」での算定に取り組んでいく方針を持たれていいたかと思いますが、取り組みについて進展はありますか?
山田様: 現状では、事業全体からの配分による算定にとどまっています。
今回の取り組みで、データ収集体制の土台は整ったと考えていますが、いかがでしょうか?
山田様: 必要最小限のGHG見える化という目的は達成できたと考えております。今後は自力で全製品の算定ができるかが課題ですが、完成車メーカー様向けの商材については対応できる見通しが立ちました。
福田様: 同感です。環境配慮型製品への要求が高まる中、再生材やバイオマス樹脂などの方向性によって対応も変わりますが、現状のCFP算定レベルは一定の合格点に達していると考えています。将来的に再生材を使用するようになれば、CFP値自体も変動しますので、その際はさらに一歩進んだノウハウが必要になるでしょう。
山田様: まずは現状を把握することが先決と感じています。GHG削減には現在の方法では限界があることは認識していますが、「何を基準に削減するか」という基本的な物差しさえなかった状況ですので、そこから始める必要があります。
削減に取り組むことでCFP値も下がりますので、非常に重要な取り組みですね。
福田様: 当面1年間は、現在のように算定対象商材を増やしていく予定です。その間に社会情勢も変化していくでしょうし、2050年に向けた長期的な視点も必要です。
山田様: おそらく近い将来、排出削減計画が具体的に示されるようになると想定しております。それに対応するためには、まず現状の数値把握が不可欠です。弊社規模ではリソースも限られていますから、まずは現状把握を行うこととしています。
福田様: 中長期的には、2030年よりも少し前の時期に次のアクションを検討する必要があると感じています。足元を固めながら、数年後には情勢の変化に合わせてより深い取り組みや新たな視点での対応が求められるかもしれません。情報収集も並行して進めていきたいと考えています。
[企業紹介]
株式会社キャットアイ
https://www.cateye.com/jp/
メールマガジン登録
担当者様が押さえるべき最新動向が分かるニュース記事や、
深く理解しておきたいトピックを解説するコラム記事を定期的にお届けします。
1
リクロマの支援について
弊社はISSB(TCFD)開示、Scope1,2,3算定・削減、CDP回答、CFP算定、研修事業等を行っています。
お客様に合わせた柔軟性の高いご支援形態で、直近2年間の総合満足度は94%以上となっております。
貴社ロードマップ作成からスポット対応まで、次年度内製化へ向けたサービス設計を駆使し、幅広くご提案差し上げております。
課題に合わせた情報提供、サービス内容のご説明やお見積り依頼も随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
⇒お問合せフォーム