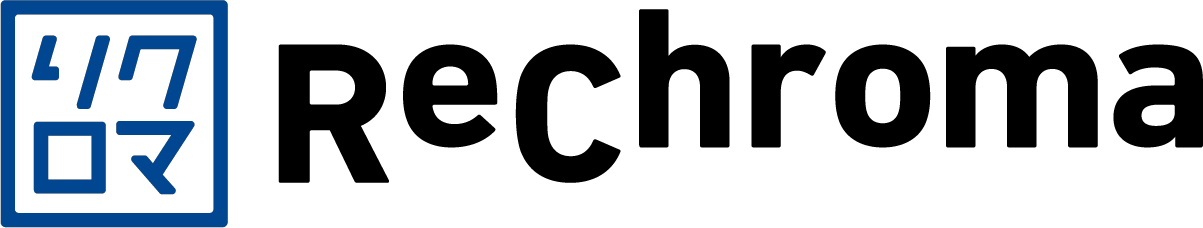Last Updated on 2025年12月28日 by Moe Yamazaki
CDPは、現在では気候変動・水セキュリティ・フォレストという3つの分野での質問書を全世界の企業に送付・評価し、回答のスコアリングデータの情報公開を行っています。
本コラムでは、CDP回答に興味がある企業に向けて、CDP回答に向けた大まかな流れや回答のポイントなどを解説します。
<サマリー>
・CDP2025質問書は、6月16日の週に回答開始
・CDP の開示項目は年々更新されるため、企業は順次対応する必要がある
CDPとは
CDPとは「人々と地球にとって、健全で豊かな経済を保つ」ことを目的に活動している国際的な環境非営利団体です。2000年に英国で設立された、国際的非政府組織(NGO)であり、気候変動、水セキュリティ、森林減少リスク・コモディティの3分野における、企業や自治体のグローバルな情報開示基盤を、投資家・企業・各国政府へ提供しています。
また、世界経済における環境報告のグローバルスタンダードとして、企業・自治体の環境インパクトに関する世界最大のデータセットを保有しており、世界中のあらゆる投資家・購買企業・政策決定者が、CDPに集められた情報を活用し、データに基づいた意思決定を行っています。
CDPと企業、投資家、サプライチェーンの関係性
まず、CDPに対して機関投資家や協同する購買企業・団体からの要請があった場合、CDPがそれらの要請を代表し、回答を求められている企業に質問書を送付します。企業はCDPが公表している質問書の回答方法のガイダンスおよび、スコアリング基準を参考に質問書に回答します。また、要請がなくとも、企業が自主的に回答することも可能です。企業の回答後、CDPは質問回答のスコアリングを行い、回答企業は多くの投資家・納入先に対して一度にスコアリングデータの情報を開示します。
CDPに対応するメリットとして、要請元の機関投資家や協同する購買企業はCDPデータをビジネスの意思決定や取引企業とのエン ゲージメントに活用できます。また一方で回答をした企業は、情報開示を通じた企業競争力の強化やその回答作業を通じて、自社が直面している 環境リスク・機会やベストプラクティスへのさらなる理解などがメリットとして挙げられます。

回答までの年間スケジュール(2025年最新)
CDP質問書の回答スケジュールは、年間を通じて行われる設計となっています。2025年の開示サイクルは下記を予定しています。
4月28日の週:回答要請機関(署名金融機関、サプライチェーンメンバー等)のポータルオープン
6月16日の週:回答開始
9月15 日の週:スコアリング対象となる回答提出期限
回答要請パターン
CDPの回答には以下の3つのパターンがあります。
1.主に機関投資家からの要請を受け、CDPが対象企業に質問書を送付
2.CDP質問書回答企業の要請を受け、CDPからサプライヤーに質問書を送付(サプライチェーンプログラム)
3.自主的にCDPの質問書に回答
回答費用
CDP回答事務費用には3つのオプションがあります。それぞれの回答費用によるベネフィットの違いは以下の通りです。
1.Essential level fee 106,000 円(+消費税)※日本企業は適用外
・CDP コーポレートダッシュボードページ等を通じた回答
・CDP ツールの利用(開示フレームワークとガイダンス)
・CDP を通じた情報開示による(投資家及び顧客等のステークホルダーとの)対話の機会
2. Foundation level fee 310,000 円(+消費税)
・上記の3つ+CDPイベントの優先的参加権限
3. Enhanced level fee 740,000 円(+消費税)
・上記の4つ+その他様々な特典
回答提出までの流れ
1.回答作成
自社の今までのTCFDレポートなどに沿って質問書への回答を作成します。過去のCDP気候変動質問書の具体的な質問についてはCDPホームページから確認することが可能です。
2.回答内容の模擬採点
CDPホームページからCDP Climate Change 2025 Scoring Methodologyというページにて、各項目、各質問の配点や採点基準が確認できるため、それらを参考に回答内容の模擬採点を行います。
3.模擬採点結果に基づき回答内容の修正
模擬採点の結果に基づき、記載の漏れ、回答のルールに添っているかなどを確認し、回答の修正をおこないます。
4.回答提出
CDPポータル上で回答を記録し、提出します。
CDPポータルの使用については、まず4月中旬に送付された回答要請メールから、アカウントの作成またはサインインを行います。 CDPポータルにて情報開示提出責任者(Disclosure Submission Lead)の設定を行い、回答事務費用の支払い手続きを完了します。その後、CDPポータル上で回答を作成し、9月15日週までに回答を提出します。
質問別の回答のポイント
回答のポイントでは、実際に回答を作成する際に気を付けたい回答記入のルールや、初めての回答の際につまづきやすいポイントをいくつか抜粋し紹介します。
CDP(気候変動質問書)の基本情報や回答メリット、ポイントを知る「CDP(気候変動質問書)入門資料」
⇒資料をダウンロードする
定義を回答する質問
定義を回答する質問については、その回答内容は当該質問のみではなく、質問書全体を通して適用されるものになるため注意が必要です。定義を回答する質問としては例として以下のものなどが挙げられます。
1. 定義を回答する質問の例
- 財務的な情報を回答する際に使用する通貨について
- 気候変動による影響を検討する際、短期・中期・長期の時間軸について
- 気候変動による影響の文脈で財務または戦略上の重大な影響について
これらの質問にて回答した定義を使用し、以下の様に他の質問に答える場合があります。
2. 前項目で回答した定義を使用する質問の例
- 貴社の事業に重大な財務的または戦略的な影響を及ぼす可能性があると特定されたリスクを記入してください。
この質問については、C2.1b で回答した財務または戦略上の重大な影響があると判断されたリスクが対象であり、そのリスクが想定される時期(短期・中期・長期)については C2.1aで回答したタイムフレームの定義に従って回答すること、そのリスクに起因する潜在的な財務影響額についてはC0.4で指定した通貨を単位として回答すること、と記載されています。
このように定義を聞かれる質問の場合には、全体を通して適用されることを意識し、他の質問との整合性を保つことがポイントです。
年・年度
年・年度については、対象期間の最終日が属する年を指すことを、質問書全体において想定されています。
例えば、気候関連目標の年や設定年を記入する欄にて、2030年4月1日〜2031年3月 31日の期間を指す年度の場合、2031と当該年度の終了年を入力します。
回答の整合性
上記の定義を回答する質問の場合、その定義の質問書全体を通しての整合性が必要とされるように、異なる質問間の回答の整合性についても正確性の評価を目的として確認が行われます。
CDPは整合性を必要とする対象の質問についても補助資料などで詳しく説明しており、どのような基準で整合性が確認されるかも対象質問ごとに明確に決められています。
自由記入欄
スコアリング基準全体を通して自由記入欄「自社固有の影響の状況」に対し、配点されています。回答を裏付けるための具体的なケーススタディを提供することでポイントが与えられる質問があり、STARアプローチという文章構成を使用することが推奨されています。STARアプローチは以下の4つの要素で構成されています。
- 状況(Situation):現状や背景はどのようなものか
- 課題(Task):何をしなければならないのか/解決すべき課題は何か
- 行動(Action):実施した一連の行動はどのようなものか
- 結果(Result):行動した結果、最終的にどのような成果が得られたか
この構成をもとにした「自社固有の影響の状況」についての十分、不十分な回答例は以下になります。
また、同じ地域で活動する企業、同じセクターの企業と区別できるような、環境問題の自社にとっての具体的な影響、自社の具体的な活動、固有の製品/サービス、について記載してください。
不十分な回答例
日本には、地震や台風、大雨などの自然災害による水害リスクにさらされている地域があります。これらのリスクは、バリュー チェーン全体で取り組むべき経営課題であると認識しています。
十分な回答例
全生産量の 3 割を占める日本国内の拠点、特にA県に立 地するC工場とD工場は沿岸部にあり、海面上昇や大雨などの自然災害による浸水リスクにあります。実際、大雨による 洪水で最大 4 週間生産が停止するなど、日本での事業の 60%が中断するリスクにさらされています。そのため、施設周 辺に堤防を設置し、浸水を防ぐためのポンプシステムを導入しています。これにより、当該工場での浸水リスクの軽減が行えました。
複雑化するCDPの全体像について体系的に理解を深めたい方はこちら!
→CDPの全体像をわかりやすく解説
CDP(気候変動質問書)の基本情報や回答メリット、ポイントを知る「CDP(気候変動質問書)入門資料」
⇒資料をダウンロードする
まとめ
本コラムでは、主にCDP気候変動質問書の回答に向けたステップと回答の際のポイントについて解説しました。CDP対応は投資家やサプライチェーンの判断基準として重要な要素になり、存在感を増しています。現在CDPの気候変動開示で用いられているTCFDをベースにした枠組みが、より厳格なISSBの枠組みに取って代わるなど、近い将来、企業はより発展的な気候開示の要求が予想されます。そのため、早期にCDP対応の準備を進め、慣れることが望ましいでしょう。
#CDP #2025
CDP(気候変動質問書)とは?
【このホワイトペーパーに含まれる内容】
・CDPの概要やその取り組みについて説明
・気候変動質問書の基本情報や回答するメリット、デメリットを詳細に解説
・気候変動質問書のスコアリング基準と回答スケジュールについてわかりやすく解説

参考文献
[1]CDP(2023)「[企業向け] CDP2023気候変動質問書 導入編」
[2]CDP (2022)「[企業向け] CDP概要と回答の進め方」
[3]CDP(2023)「2023年 CDP気候変動質問書 回答に向けて(補助資料)」
[5]CDP(2022)「CDPからの情報提供:リーディングテナント行動方針に係るセミナー」
リクロマの支援について
弊社はISSB(TCFD)開示、Scope1,2,3算定・削減、CDP回答、CFP算定、研修事業等を行っています。
お客様に合わせた柔軟性の高いご支援形態で、直近2年間の総合満足度は94%以上となっております。
貴社ロードマップ作成からスポット対応まで、次年度内製化へ向けたサービス設計を駆使し、幅広くご提案差し上げております。
課題に合わせた情報提供、サービス内容のご説明やお見積り依頼も随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
⇒お問合せフォーム