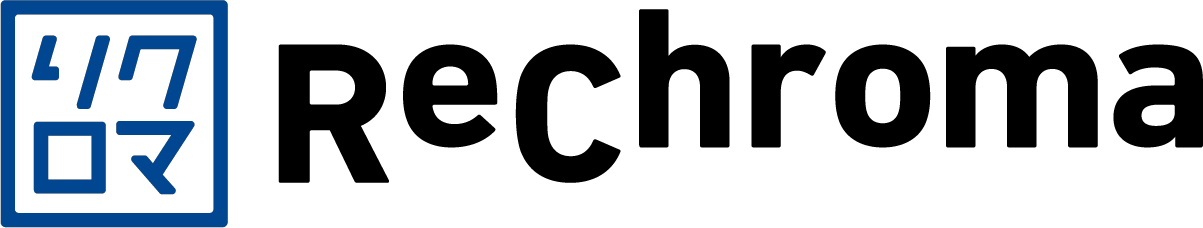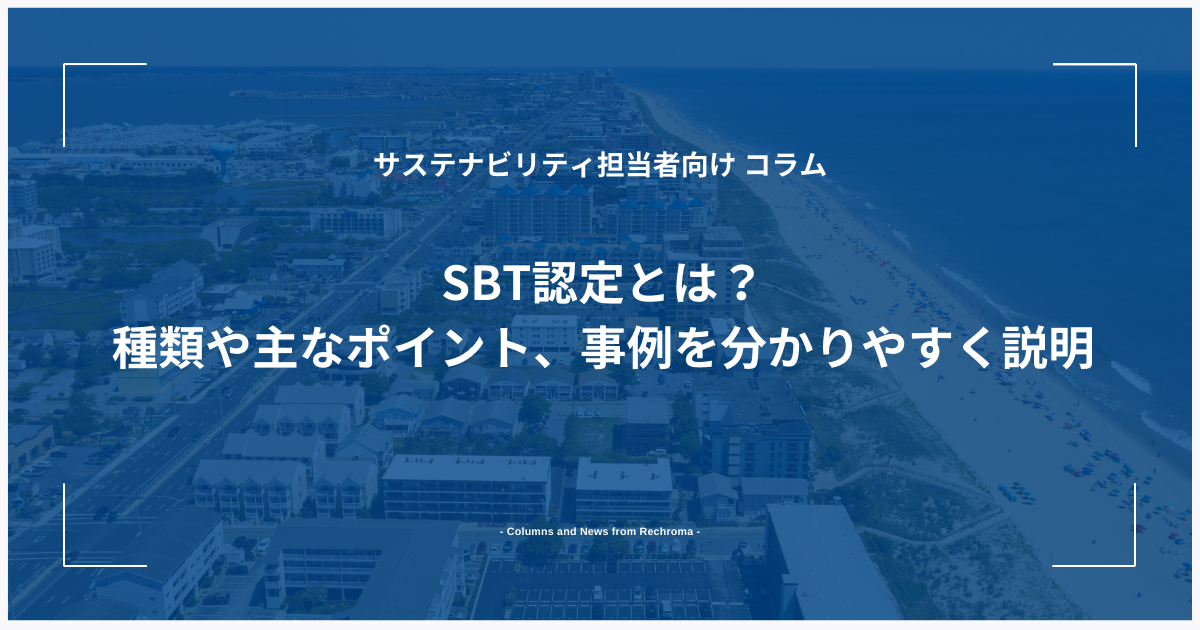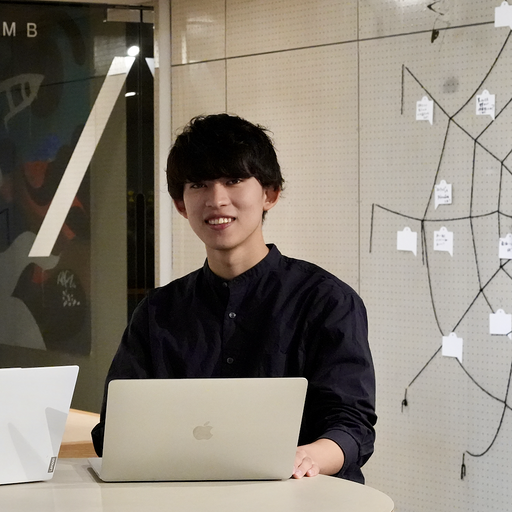Last Updated on 2026年1月5日 by Sayaka Kudo
【気候変動関連用語がまるわかり!用語集はこちら】

SBT認定の対応を進めている企業が多い中、SBTの申請プロセスにおいて、複数の参照資料や英語での申請に困ってしまう担当者様もいるのではないでしょうか。本コラムでは、SBTの基本概要・SBTの種類・SBT申請手順をわかりやすく解説します。
SBTとは
SBTとは「Science Based Targets」(科学と整合した削減目標)の略称で、SBTイニシアチブ(以下SBTi)が作成しています。この削減目標は、世界の平均気温の上昇を産業革命前の水準よりも1.5度未満に抑えることを目指しています。これらの数値は科学的な知見と整合しており、世界の平均気温の上昇を産業革命前の水準よりも1.5度未満に抑えることを目指しています。
2014年9月に4つの国際団体(CDP、WRI、WWF、UNGC)が運営主体となりSBTiを設立しました。このSBTiが企業に対して削減目標の設定を求めていて、企業が設定した目標が基準に整合しているかを検証しています。
リクロマのSBT取得支援についてはこちらからご覧いただけます。
→SBT認証取得支援
SBTの種類― 短期・長期・ネットゼロ
SBTの目標は、「短期目標」「長期目標」「ネットゼロ目標」の3層構造で構成されています。
短期目標は5〜10年先を対象とし、長期目標は削減対象範囲の90%以上の削減を求めます。
ネットゼロ目標は長期目標に加えて、残留排出量の除去・相殺を含む「実質ゼロ」を目指す目標です。
そのため、ネットゼロを設定する場合は長期目標の設定が必須となります。
上記に加えて、中小企業向けのSBTが存在します。また、産業分野別の目標も存在します。特定の産業分野に焦点を当てた目標で、産業分野の特性を踏まえた削減目標となっています。産業分野の種類や基準については本記事の4番で説明します。
自社がネットゼロ目標を取得するのか、また中小企業向けや産業別のSBTに該当するかを把握し、適切な基準を使用することが大切です。
SBT取得企業の動向
日本におけるSBT取得企業は、2018年度以降増加傾向にあります。世界全体をみても日本ではSBTの取得企業は比較的多いです。
下記の表における「コミット」とは、24ヶ月以内にSBTを設定し、妥当性確認のために提出しますという意思表明を事務局にした状態を指します 。この表に記載されている時期以降(2023年度以降)も毎週のようにコミットした企業がSBTi公式ホームページに掲載されていることから、今後もこの増加傾向は続くことが予想されます。
日本のSBT取得企業数

SBT認証を取得するメリット
SBTを取得するメリットとして、投資家と顧客双方に対する自社の魅力向上に繋がることが挙げられます。また、社内においても様々な効果が期待できます。
SBTを取得するメリットについて詳しい記事はこちら!
⇒SBTを取得するメリットとは?分かりやすく解説
投資家への魅力
SBTは気候変動に対する先進的な取り組みを行っていることを示します。SBTiがコミットした企業の役員に行った調査によれば、52%が投資家の信頼性向上につながったと回答しました。また、SBTの取得はCDPやWBCSD削減貢献量等の投資家が注視するイニシアチブでの評価向上にもつながります。
具体的な例としては、下記の通りです。
- CDPにおいては、「リーダーシップ」、「マネジメント」、「認識」、「情報開示」での得点向上につながります。
- WBCSDの削減貢献量ガイダンスにおいては、SBTを取得することで、削減貢献量主張の前提となる「自社の適格性」要件を充足します。
- 格付機関・CDP対応の強化:SBT目標の設定は、ESG格付機関やCDPなど外部評価で配点上位項目に位置付けられる傾向が強まっており、投資家対応上の戦略的意義が高いです。
顧客への魅力
SBTの取得は顧客にとっても大きな魅力となります。エシカル消費やSDGsの概念が注目され、海外取引先からの要請が高まる中で、持続可能性に対するブランドの評判が重要になっています。
また、SBTのScope3削減目標を設定している企業の中には「サプライヤーの一定割合にSBT目標を設定させる」ことを自社目標に含めている企業もあります。SBT目標の設定はこのような需要に応えることになります。
※「サプライヤーにSBT目標を設定させる」ことを目標に含めている企業例[2]
大和ハウス工業、第一三共、ナブテスコ、大日本印刷、イオン、武田薬品工業、国際航業、ロッテ、ソニーグループ等。
社内における魅力
今後各国政府がさらにパリ協定の実施に取り組み続け、排出量の多い活動の規制強化が想定されます。SBT認証を取得することで、それらの規制に対するレジリエンスが高まると期待できます。
また、SBTiのホームページに記載されているソニーのケーススタディ[3]ではSBTの取得が社内のイノベーションに役立ったという事例が掲載されています。目標達成のための行動として排出量削減を促進する結果、新たな製品や製造プロセスを開発できることが期待できます。
加えて、SBT目標の設定・運用は、経営層を巻き込んだ全社的な意識変革を促し、自己拘束的なガバナンスの形成にも寄与します。中長期的な削減目標を社内外に明示することで、環境対応を単なるCSRではなく、経営戦略の中核に据える機運が高まります。
SBT 短期目標の設定方法
短期目標は、SBT認証取得に向けて全ての企業が設定する5~10年後を目標年とした削減目標です。この章では、短期目標の主なポイントや企業事例を説明します。
SBT短期目標についての詳しい記事はこちら!
⇒SBT 短期目標の取得ポイントは?基準について詳しく解説
①企業範囲
SBTの目標設定は、子会社を含んだ企業全体での設定が必要です。子会社の範囲はGHGプロトコルに沿って除外なく算定し、財務会計等で使用される境界と一致させることが推奨されています。
目標は親会社またはグループ全体でのみの提出が推奨されています。子会社が独自に目標を設定することも可能ですが、親会社の目標には子会社の排出量も含める必要があります。そのため、はじめから親会社またはグループ全体で認証を取得して削減に取り組む方が二重の目標設定にならずに済むと考えられます。
②排出量の対象範囲
Scope1,2に関しては前提として企業全体の排出量をおさえることが必要です。二酸化炭素のみでは不十分で、フロンやメタンなどの温室効果ガスすべてを対象としていることに注意しましょう。ただし、理由を説明すれば実績と目標の両方において5%までは除外が認められています。
一方、Scope3に関しては排出量がScope1,2,3排出量の合計の40%以上の場合に目標に含める必要があります。(天然ガスやその他の化石燃料の販売や流通に関与する企業はScope3の割合に関わらずカテゴリ11の目標設定が必要です。)削減対象かどうかの判断のために、どんなにScope3が少ないと考えられてもまずはScope3を算定して全体に占める割合を確認する必要があります。
目標設定においては、Scope3全体の2/3をカバーする目標を設定する必要があります。排出削減のみならず、サプライヤーや顧客にSBTの目標を設定してもらう「サプライヤー/顧客エンゲージメント目標」の設定も認められています。
③時間軸
先述の通り、短期目標の達成年である目標年は提出日から5〜10年先に設定します。近年では2035年を目標年とする企業が増加しています。10年先以上の目標はネットゼロ目標としての提出となり、ネットゼロ目標の基準と整合させなければなりません。
また基準年は、2015年以降であることが要件で、基準年が申請年から3年以上前の場合、直近2年のいずれかの年を直近年として排出量を報告する必要があります。
④目標設定
Scope1,2,3全てにおいて、SBTiが公表している計算ツールを使用して削減目標の排出量を計算します。
Scope1,2の削減目標は、産業革命前と比較して1.5℃以内の上昇に抑える水準であることが必要です。原単位目標はセクター別(産業別)の限られた場合に有効なため、基本は総量削減となります。また、Scope2削減目標の代替として、再エネ電力を積極的に調達する目標も設定することが可能です。
一方、Scope3の削減目標は産業革命前と比較して可能な限り1.5℃水準と整合させることが推奨されます。サプライヤー/顧客エンゲージメント目標は、目標年に関係なく提出日から遅くとも5年以内の達成が求められているため、注意が必要です。
上記以外にも様々な基準や推奨事項が存在し、これらは全て「SBTi Corporate near-term criteria」に記載されています。資料は定期的に更新されているため、目標設定の際に最新版かどうかの確認が必要です。
合わせて読みたい
→SBT取得支援事例はこちら
SBT 短期目標設定の企業事例
鹿島建設株式会社
鹿島建設株式会社は、鹿島グループとして2023年にSBTの短期目標の認定を取得しています。2030年度を目標年として、Scope1,2を42%減、Scope3(カテゴリ1とカテゴリ11)の25%減を設定しています。(2021年度比)環境ビジョンで「脱炭素」を一つの視点として捉え、排出量削減の指標としてSBTの目標を使用しています。
参考:気温上昇を1.5℃に抑えるSBT認定を取得 | プレスリリース | 鹿島建設株式会社 (kajima.co.jp)
オムロン株式会社
オムロン株式会社は、2022年に認証を取得しています。2030年度を目標年として、Scope1,2を65%減、Scope3(カテゴリ11)の18%減を設定しています。(2016年度比)達成のための取り組みとして、省エネの徹底や電力のクリーン化、省エネ・省資源を推進しています。
参考:
「Science Based Targetsイニシアチブ」の認定を取得 | オムロン (omron.com)
スコープ1・2 | 環境 | サステナビリティ | オムロン (omron.com)
SBT ネットゼロ目標設定の基準
ネットゼロとは温室効果ガスの排出量を「実質ゼロ」にする考え方です。ただし完全に排出をゼロにするのは難しいため、除去困難な残りの排出量は大気からの吸収量を排出量から差し引いて相殺します。先述の通りSBTのネットゼロ目標の設定は長期目標として必須ではありませんが、SBTiは現在、ネットゼロ標準(Corporate Net-Zero Standard)の採用を強く推奨しており、これは世界の排出量削減目標との整合性を高めるための世界で唯一のフレームワークです 。基準は短期目標と比較して厳しいですが、設定することで気候変動の対応において大きなアドバンテージとなり、外部評価が向上することが予想されます。
①企業範囲
ネットゼロ目標においても、短期目標と同様にグループ全体での提出が推奨されています。
②算定対象の範囲
ネットゼロ目標においては、スコープ1,2,3の全てを目標に含める必要があります(5%までは除外可能)。スコープ3の目標設定が必須となり、短期目標と大きく異なる点のため注意が必要です。
③時間軸
基準年は2015年以前は認められておらず、短期目標と同じ基準年を使用することが推奨されています。また、目標年は2050年までで設定します。
④目標設定
2050年までに1.5度水準と整合するために、企業がどれだけ排出量をどれだけ削減するかを示します。長期目標では毎年の削減量は設定されておらず、スコープ1,2,3全体の90%を削減することのみが求められています。スコープ1,2,3全体で設定することも、スコープ1,2とスコープ3で区別して設定することも可能です。
短期目標と同様に考慮するべき様々な事項が存在し、これらは全て「Net-Zero-Standard.pdf 」と「Net-Zero-Standard-Criteria.pdf」に記載されています。(リンク先は2025年9月)さらに、SBTiのV2ドラフト(2025年公表)では、今後の制度改定として以下の方向性が示されています。このため、ネットゼロ目標を設定する企業は、早期にデータ整備と検証体制の構築を進めることが重要になります。
・スコープ1・2・3を個別に目標設定することが原則化される見込みであり、従来の一括目標設定よりも詳細な管理が求められるようになります。
・削減量の算定方法の厳格化に加え、第三者による保証(検証)の取得が必須化される方向です。
SBTネットゼロ目標についての詳しい記事はこちら!
⇒SBT ネットゼロとは?概要や取得事例をわかりやすく解説
SBT ネットゼロ目標設定の企業事例
ソニーグループ株式会社
ソニーグループ株式会社は、2022年にネットゼロ目標を取得しました。「環境負荷ゼロ」を実現するために環境計画「Road to Zero」を推進し、2030年までにスコープ1,2のネットゼロ達成を目指し、2040年までにスコープ1,2,3全体でネットゼロを目標としています。
バリューチェーン全体でネットゼロ目標を達成するために、調達先との協力、バリューチェーン全体で総量目標を統一する、使用後まで考えた環境活動などを行っています。
参考:ソニーグループポータル | ソニーの環境計画 (sony.com)
アスクル株式会社
アスクル株式会社は、2024年3月にネットゼロ目標を取得しました。2021年を基準年として、スコープ1,2,3の2050年におけるネットゼロを目標としています。
アスクル株式会社は2016年に「2030年CO2チャレンジ」を宣言し、現在にかけて様々な取り組みを行っています。今後さらに2050年までのネットゼロを目指し、サプライチェーン全体でのCO2削減に取り組むとしています。
参考:環境経営 | 環境 | アスクル – 環境・社会活動報告 (disclosure.site)
中小企業向けSBTと産業別SBT
SBTiは、中小企業に向けて独自の目標を設定しています。通常のSBTと比べ、負担が少なく着手が容易であるという特徴があります。
ただし、SBTiは「中小企業」を以下のように定義しているため、自社が該当するかどうかを確認する必要があります。
| 【排出量基準(全て満たす必要あり)】 | Scope1とScope2(ロケーション基準)の合計が10,000t-CO2e未満であること。 |
| 【セクター・子会社による除外基準(全て満たす必要あり)】 | 「金融機関」または「石油・ガス」産業に分類されないこと、セクター別SBT目標の設定が求められないこと、通常のSBTで申請が求められる会社の子会社でないこと。 |
| 【財務・従業員基準(4項目のうち3つ以上を満たす必要あり)】 | 従業員が250人未満、売り上げが5,000万ユーロ未満、総資産が2,500万ユーロ未満、FLAG産業ではない 。 |
詳しくはこちら!
→【2024年1月改訂】中小企業向けSBTとは?
産業別(セクター別)のSBT
SBTの短期目標とネットゼロ目標は全企業に向けた基準となっていますが、産業によってはその基準に沿った削減が難しい企業様もいらっしゃるのではないでしょうか。SBTiは、この削減が難しいと考えられる産業別にガイダンスを公開していて、「セクター別」とあらわしています。セクター別のガイダンスでは最低の野心レベルが設定され、そのレベルに応じた目標設定が求められます。
現在基準が確定または開発中のセクターは以下の通りです。他のセクターにおいても今後ガイダンスが新たに公開されたり、内容が変更する可能性があるため注意深く確認する必要があります。
| Criteriaが公開済み | Criteriaが未公開 |
| ・アパレルとフットウェア・セメント・金融機関・森林、土地、農業(FLAG)・情報通信技術(ICT)・海運・電力・鋼鉄・航空・建物・化学薬品・石油、ガス・輸送 | ・化学品・自動車・電力 |
ポータル化したSBT 目標の申請方法
2025年以降、SBTiの提出方法は専用ポータルへの直接入力に完全移行しました。以前のExcelアップロード方式は廃止され、ポータル上でフォーム入力・証拠資料アップロード・審査進行まで一元管理されます。この変更により、申請から審査完了までの平均期間も約2〜3ヶ月に短縮されています。
まとめ
この記事では、SBTの概要と種類、申請の流れのポイントについて解説しました。SBT認定は、もはや「一部の先進企業の取り組み」ではなく、投資家やサプライチェーンの要請によって標準的な経営課題となりつつあります。日本企業は世界的にも取得数が多く、特にプライム上場・CDP開示企業を中心に動きが加速しています。2025年以降、ネットゼロV2や第三者検証の必須化などハードルは上がりますが、早期のコミットメントが将来的な信頼と優位性を確保する鍵となります。
#SBT
SBTとは?その種類と申請プロセスをわかりやすく説明
【このホワイトペーパーに含まれる内容】
・SBTの概要と主な基準について説明
・短期目標とネットゼロ目標についてそれぞれ解説
・申請プロセスをステップごとに詳細に解説

参考文献
[1]環境省(2023)「SBTに参加している国別企業数」(閲覧日:2026年1月5日)
[2]Science Based Targets「ケーススタディ – Sony – Science Based Targets」(閲覧日:2026年1月5日)
[3]Science Based Targets 「中小企業(SME)として目標を設定する – 科学的根拠に基づく目標 (sciencebasedtargets.org)」(閲覧日:2026年1月5日)
[4]Science Based Targets 「セクターガイダンス – 科学的根拠に基づく目標 (sciencebasedtargets.org)」(閲覧日:2026年1月5日)
リクロマの支援について
弊社はISSB(TCFD)開示、Scope1,2,3算定・削減、CDP回答、CFP算定、研修事業等を行っています。
お客様に合わせた柔軟性の高いご支援形態で、直近2年間の総合満足度は94%以上となっております。
貴社ロードマップ作成からスポット対応まで、次年度内製化へ向けたサービス設計を駆使し、幅広くご提案差し上げております。
課題に合わせた情報提供、サービス内容のご説明やお見積り依頼も随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
⇒お問合せフォーム