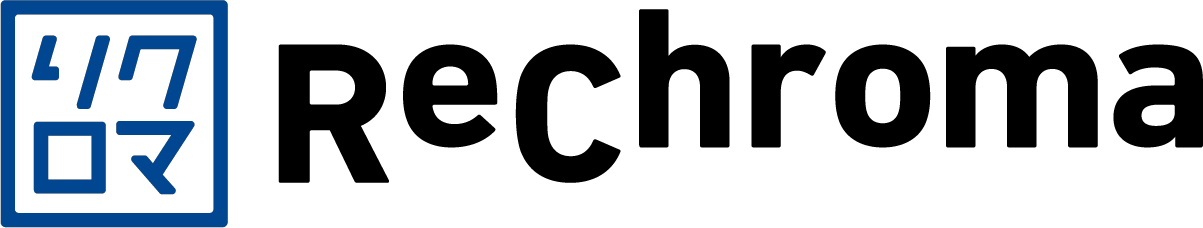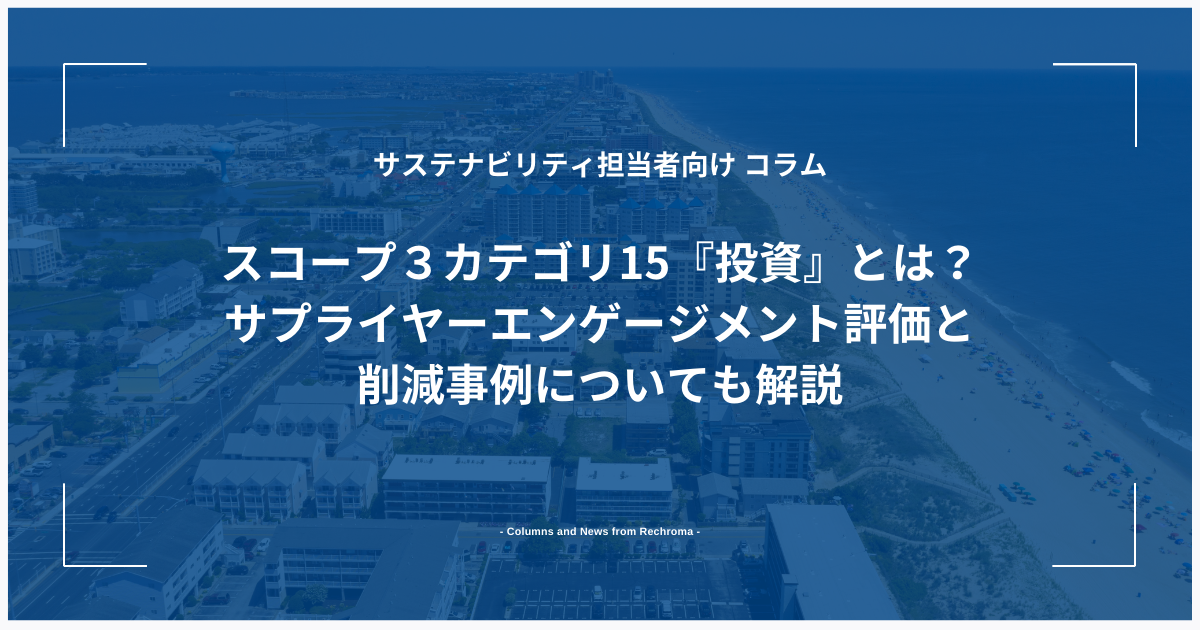Last Updated on 2025年12月31日 by Moe Yamazaki
【気候変動関連用語がまるわかり!用語集はこちら】
スコープ3カテゴリ15「投資」は、金融機関や投資事業者に特化したカテゴリで、投資活動を通じて発生する間接排出量を対象としています。近年、投資先企業が排出する温室効果ガスの削減に取り組む姿勢が、金融業界の持続可能性や投資判断において重要な指標となりつつあります。
この記事では、カテゴリ15の基本的な仕組みや算定の考え方を解説するとともに、投資活動を通じた環境負荷軽減の具体的な事例を紹介します。
サマリー
• スコープ3カテゴリ15は投資活動による間接排出量を対象
• 出資比率を基に投資先の排出量を算定
• 投資先の排出削減を支援する取り組みが重要
• データ収集とモニタリングが管理の鍵
• 持続可能な投資方針が企業の環境価値を高める
関連記事はこちら!
⇒スコープ3カテゴリ12『販売した製品の廃棄』とは?サプライヤーエンゲージメント評価と排出削減事例についても解説
⇒カテゴリ1『購入した製品およびサービス』とは? 算定方法や排出削減事例についても解説
スコープ3カテゴリ15とは
スコープ3は、Scope2に含まれないすべての間接排出(他社が排出源となるもの)を対象とし、発電や熱生成時の排出を除いた全15カテゴリの活動に細分化されている排出量の範囲を指します。
そのうちのカテゴリ15は、投資の運用に伴い発生する排出量を対象としており、金融機関や投資家がその投資活動による環境負荷を評価し、削減のための具体的な取り組みを進めることが求められています。
投資活動は、直接的に排出量を生じさせるだけでなく、投資先企業の行動を左右する力を持っています。金融機関が持続可能な投資ポリシーを採用することで、脱炭素経済への移行を加速する効果が期待されます。
特に、グリーンボンドやESG投資が注目される中で、カテゴリ15の適切な算定と管理は、企業価値向上にも繋がる重要な要素です。
算定方法
カテゴリ15の算定は、投資先のScope1・2排出量に出資比率を掛け合わせる「Equity share approach」が一般的ですが、近年はPCAFガイドラインに基づく算定が推奨されています。投資先のデータ収集は、公開データ(SHK法や温帯法など)の利用に加え、投資先への直接ヒアリングによる一次データ収集も行われています。特に金融機関は、自社で構築した算定システムを投資先に展開し、中小企業を含む幅広い投資先のデータを効率的に収集する事例も増えています。
例として、以下のような現実的な方法が挙げられます。
1.投資先の排出量データ収集
投資先企業やプロジェクトからScope1およびScope2排出量に関するデータを取得します。これには、投資先の年次報告書や持続可能性レポートが活用されることが多いです。
2.出資比率を適用
投資先の排出量に対して、自社の出資比率を掛け合わせます。たとえば、ある企業の年間排出量が100,000トンCO₂で、自社の出資比率が25%であれば、自社のカテゴリ15として計上する排出量は25,000トンCO₂となります。
3.補完データの利用
投資先の排出データが入手できない場合は、同業界や類似プロジェクトのデータを活用して推計します。この手法はデータ不足時の代替策として現実的とされています。
この算定方法は、排出データが不完全な場合でも活用できる柔軟性が特徴であり、特に幅広い投資ポートフォリオを持つ金融機関に適しています。
ただし、データの信頼性や算定基準の整合性を保つためには、継続的なモニタリングと更新が重要です。資先企業が掲げる排出削減目標に対して進捗があるかを定期的に確認し、必要に応じて投資ポリシーを調整する必要があるでしょう。
投資先エンゲージメントとスコープ3カテゴリ15
スコープ3削減の文脈では、しばしば「サプライヤーエンゲージメント」が重要とされます。これは、企業が取引先と協力し、バリューチェーン全体で排出削減を進める取り組みです。
カテゴリ15においては、この考え方が「投資先エンゲージメント」として求められます。金融機関や投資家は投資先に対して排出量の算定や削減を促し、その結果を自社のScope3カテゴリ15に反映させる必要があります。現在の対象はScope1・2が中心ですが、将来的にScope3排出量も含まれる可能性が議論されており、早期から投資先への働きかけを進めることが望まれます。
次の記事はこちら!
⇒カテゴリ1『購入した製品およびサービス』とは? 算定方法や排出削減事例についても解説
スコープ3排出削減の企業事例
最後に、サプライヤーとの協力を通じてスコープ3排出削減を推進している株式会社セブン&アイ・ホールディングスの取り組みを紹介します。
※環境省モデル企業事例集より引用
会社事業概要
株式会社セブン&アイ・ホールディングスは、セブンイレブン、イトーヨーカドーなど多数の店舗を展開する総合流通グループです。同社では、スコープ3が全体排出量の約90%を占めており、特にサプライヤーと連携した排出削減が重要なテーマとなっています。
多くのサプライヤーを抱える同社は、サプライチェーン全体の脱炭素化に向けて、支援と協力を軸にした取り組みを進めています。
取り組み①サプライヤーの排出削減計画のモデルケース作成
セブン&アイ・ホールディングスは、まずサプライヤーが排出削減計画を策定しやすくするためのモデルケースを作成しました。
このモデルケースでは、製造、輸送、廃棄といった各段階における排出削減施策を具体的に示し、サプライヤーがそれを参考にしながら独自の計画を構築できるようサポートしています。
たとえば、エネルギー効率の向上や低炭素素材の使用を含む具体的な施策が挙げられています。このアプローチにより、サプライヤーの負担を軽減し、効果的な削減計画の策定を促進しています。
取り組み②サプライヤーの排出削減支援体制の構築
セブン&アイ・ホールディングスは、サプライヤーが自律的に排出削減を進められるよう支援体制の整備に注力しています。この取り組みは、短期的な削減目標の達成だけでなく、長期的な持続可能性を目指したサプライチェーン全体の改革を目的としています。
具体的には、サプライヤーに対して排出削減目標の設定を支援し、その進捗を管理できるデジタルツールを提供しています。これにより、各サプライヤーが自社の状況に応じたデータを集計し、リアルタイムで進捗を把握できる仕組みを実現しました。
また、脱炭素化に必要な知識やスキルを共有するため、定期的なトレーニングプログラムやワークショップを開催しています。これらの場では、実践的な削減事例や先進技術の導入方法が共有され、サプライヤー同士の連携を深める機会も提供されています。
まとめ
スコープ3カテゴリ15「投資」は、金融機関や投資事業者が持続可能な社会を実現する上で重要な役割を果たす領域です。
投資先の排出量を正確に把握し、削減計画を支援することは、企業全体の環境目標達成に直結し、また投資活動を通じて脱炭素経済を支援することは、長期的な投資価値の向上にも寄与します。
そしてカテゴリ15を効果的に管理するためには、投資先企業との連携を深めるだけでなく、持続可能な投資基準を整備し、透明性の高い意思決定プロセスを確立することが必要です。こうした取り組みを通じて、金融機関自身が社会的責任を果たします。
リクロマでは、Scope1,2,3における排出量算定や削減計画の立案をサポートしています。企業の脱炭素経営を推進するための最適な解決策をご提供しますので、お気軽にお問い合わせください。
次の記事はこちら!
⇒カテゴリ1『購入した製品およびサービス』とは? 算定方法や排出削減事例についても解説
参考文献
環境省 スコープ3排出量の算定技術ガイダンス
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/(J)-calculation_guidance.pdf
CDP2023 サプライヤーエンゲージメント評価 イントロダクション
https://cdn.cdp.net/cdp-production/comfy/cms/files/files/000/008/101/original/SER_Introduction_JPN_2023.pdf
環境省 サプライチェーン排出量算定に関する説明会 Scope3~算定編~
https://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/files/dms_trends/study_meeting_2020.pdf
環境省モデル企業事例集
https://www.env.go.jp/content/000118181.pdf
\ スコープ3算定式の精緻化を図る!/
Scope3の概要と削減方法、削減好事例、及び過去の支援を通じて頻繁に
頂いていた質問のQ&Aを取りまとめ、資料を制作いたしました。
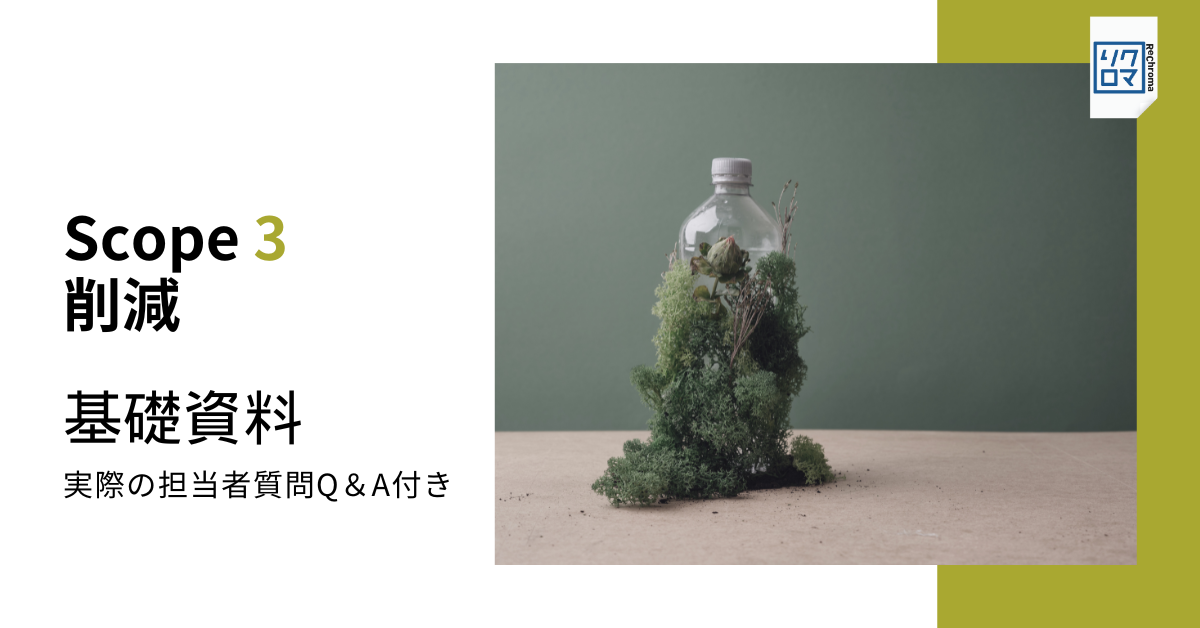
リクロマの支援について
弊社はISSB(TCFD)開示、Scope1,2,3算定・削減、CDP回答、CFP算定、研修事業等を行っています。
お客様に合わせた柔軟性の高いご支援形態で、直近2年間の総合満足度は94%以上となっております。
貴社ロードマップ作成からスポット対応まで、次年度内製化へ向けたサービス設計を駆使し、幅広くご提案差し上げております。
課題に合わせた情報提供、サービス内容のご説明やお見積り依頼も随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
⇒お問合せフォーム