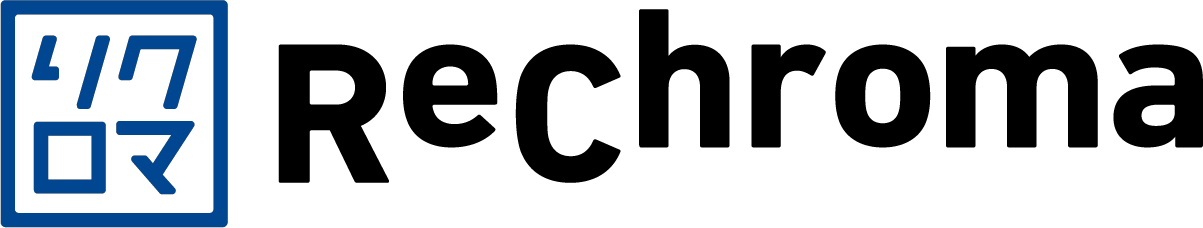Last Updated on 2025年6月17日 by Moe Yamazaki
【気候変動関連用語がまるわかり!用語集はこちら】
本コラムではそのレポートを参考にCDPのこれまでの動向を振り返ると共に、2025年のスコアアップにつながるポイントについて解説します。
<サマリー>
・2024年度の質問書は主に4つの変更点がある(1. 気候変動と水セキュリティと森林の統合、2. TCFDやIFRSとの整合性強化 、3. 金融セクター向け開示項目の整理、 4.中小企業向け開示項目の整理)
・IFRS S2の反映や気候変動以外のテーマ(水セキュリティ、フォレスト、プラスチックなど)の理解が高スコアの鍵になる
CDP2024の全体像についてはこちら!
⇒【Part 1】CDP2024の全体像を先取り CDP 2024年度の押さえておくべき変更点とは?
トリプルA評価を受けた企業事例についてはこちら!
→CDP回答者必見 CDP2023質問書でトリプルA評価を受けた企業の好事例3選
弊社のサービス紹介はこちら!
→サービス資料をダウンロードする
CDP2024年の変更点
質問書の統合
2024年度のCDP気候変動スコアレポートの大きな変更点として挙げられるのが、以下の4点です。
- 3つの質問書の統合
- IFRS S2、ESRS、TNFDなど国際フレームワークとの整合性の強化
- 金融サービス企業向け質問書の統合と質問項目の整理
- 中小企業向けの質問書の置き換え
特に2023年まで「気候変動」、「水セキュリティ」、「森林」の3つに分かれていた質問書が統合されるのは大きな変化となります。
3つの質問書の項目はテーマが被る領域も多いため重複する質問事項が多かったですが、これらが1つに統合されたことで担当者の回答の負担が減少し、企業は環境保護活動の取り組みを包括的に情報開示しやすくなったといえるでしょう。
CDP2024年の変更点について詳しく理解したい方はこちら!
→CDP2024の全体像を先取り CDP 2024年度の押さえておくべき変更点とは?【Part 1】
気候変動開示の基準がTCFDからISSBへ
2024年よりCDPの気候変動開示で用いられる枠組みが、 TCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)基準のものからISSB(国際サステナビリティ基準審議会)の「気候関連開示(IFRS S2)」をベースにしたものに反映されます。
ISSBにおける要求はスコープ3の温室効果ガス排出量の開示や定性的なシナリオ分析の実施を義務付けるなど、TCFDのものよりも厳格であるため、CDPのスコアリングを改善させる際には十分に考慮する必要があります。
これにより、CDPのスコアリングレポートの質問書の各項目に明確に答えていれば、ISSBも自動的に対応しているということになります。
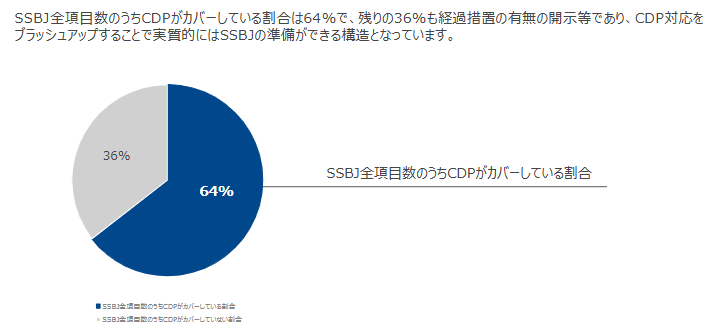
CDP2025質問書の回答で留意するべきポイント
基本編:STARアプローチの採用
質問書全体を通して基本的なポイントは、自由記述はSTAR方式と自社固有性を意識することです。そうしたポイントに留意しながら一旦作成した回答を、スコアリング基準と照らし合わせてブラッシュアップしていくことがより良いスコアメイキングにつながります。
自由記述は回答者が所属する企業の固有の状況に合わせたケーススタディを記載するもので、STARアプローチと呼ばれる以下の4基準によってスコアリングされます。
- 状況(Situation):現状や背景はどのようなものか
- 課題(Task):何をしなければならないのか/解決すべき課題は何か
- 行動(Action):実施した一連の行動はどのようなものか
- 結果(Result):行動した結果、最終的にどのような成果が得られたか
質問の回答には正確な地名や数値を盛り込む必要があり、自社の状況をよく反映させる必要があることには注意しましょう。
具体的な質問や解答例についてはこちらの記事をご参照ください。
基本編:未実施の項目は実施していないと記載
CDPは定義に関する質問の一貫性を重視しており、企業特有の事例を明確に掲載する必要があります。
やっていない項目を無理やり記入しても、よい採点結果を得ることはできません。
一方で、空欄の場合は無回答扱いになってしますため、未実施の項目については、「実施していない」という旨を記載することで最低限の点数を取ることが可能です。
点数を減らさないためにもそのように回答するようにしましょう。
応用編:IFRS S2の反映
CDPに回答する際、IFRS S2の内容を意識して記載すると高スコアを狙える可能性があります。IFRS S2は、気候関連のリスク及び機会の情報開示枠組みであり、TCFD の後釜として同じ4本の柱(ガバナンス、戦略、リスク機会、指標と目標)を定めています。IFRS S2の開示要求は、CDPのものよりも詳細にわたる部分があるためです。
ここでは、項目別にCDPの質問例と反映するべき点を解説していきます。
IFRS S2については「ISSB最終案 IFRS S2とは?」をご参照ください。
ガバナンス
IFRS S2ではガバナンス機関(取締役会や委員会など)だけでなく個人に対して、以下のようなことを開示することを求めています。
・責任の所在や職務や権限への反映の方法
・監督するための適切な能力の有無や今後の開発方針
・事業戦略等の意思決定およびリスク管理プロセスの監督における気候関連リスク・機会の考慮状況報告を受けるプロセスや頻度などの監督体制
戦略
IFRS S2では、気候変動に対するリスクと機会が現在と将来の企業戦略と意思決定に与える影響については、移行計画を含めて開示するよう定めています。
特に、石炭火力発電や炭鉱事業など温室効果ガスやエネルギー、水を大量に消費する事業の廃止または縮小計画、サステナビリティの強化のための追加的な資本拠出や研究開発、サプライチェーンや需要の変化に起因する資源配分などがあれば、高スコアが望めるので確実に掲載するようにしましょう。
さらにIFRS S2では技術や能力、資源がない場合は記載不要ではあるものの、キャッシュフローや財務パフォーマンス、財政状態に与える影響や予測される事柄について現在や将来(特に次の年次報告期間内)に影響を与えるものについて開示することも求めています。
リスク管理
IFRS S2では気候変動に関連する機会・リスクを特定・評価・優先受けして監視するためのプロセスやその程度についての管理方法を問いています。
リスクの種類や考慮だけでなく、対策の順位づけなどより具体的な施策について回答が必要です。
指標と目標
IFRS S2では温室効果ガスの排出に関して、以下の情報が必要と定めています。
- 業種に関わらない横断的な指標(スコープ1,2,3の温室効果ガス排出量、内部炭素価格、役員報酬など)
- 業種ベースの測定基準
- 機構関連の企業が戦略に関して設定した目標や、法律などで達成が求められている目標に関する情報(例:温室効果ガス排出量に関する目標)
- ,目標に関する第三者による検証の有無など
- 温室効果ガス排出量に関する目標の説明(例:目標の達成となるスコープなど)
特にスコープ1の7ガスについては、IPCCの最新換算係数(AR6)を使用する必要があり、現行の環境省のもの(AR4)よりも厳しい基準であることには注意したほうがいいと言えるでしょう。
また自社活動だけでなくバリューチェーン全体を含めた温室効果ガスの削減を考慮に入れた、スコープ3の開示が要求されていることにも注意が必要です。
応用編:その他のテーマについて
CDPでは気候変動だけでなく、水や森林、プラスチック、生物多様性など様々な問題に対するサステナビリティに向けた取り組みを評価しています。
2024年は質問書が1つに統合されますが、質問項目にはそれらの情報を多く加わることが想定されるため、高スコアを狙う場合は必ず考慮するようにしてください。
なお、水セキュリティについてはこちらの記事に、プラスチックや森林についてはこちらの記事により詳しい内容を記載しているので、参考にしてみてください。
水セキュリティ
干ばつや水害などの自然災害、氷河の後退、砂漠化などにより企業利用できる淡水資源の枯渇に対する戦略を水セキュリティといいます。
投資家からの注目も高く、日本でも回答数が2023年に前年比2.7倍にまで膨れ上がった項目です。
今後は質問書の統合により回答する企業がさらに増えることが予想されます。
水リスクについてはこちら!
⇒水リスクにおける「評価ツール」とは?種類や実際の使用例も紹介
プラスチック
プラスチックは2024年の採点項目から外れましたが、水セキュリティやバリューチェーン全体に大きく関わるだけにCDPでも重視されています。
2024年は公的機関とSMEs以外の全ての企業体にベーシックポイントが適用され、食品や飲料などプラスチックの影響が大きい業界に対してはより多くの質問が科されるようになるため注意するようにお願いします。
また活動範囲も従来はプラスチックを用いた商品の生産・販売だけでしたが、2024年より「廃棄物または/および水マネジメント活動の展望」や「プラスチック関連活動のための金融商品・サービスの提供」も入りますます後半に適用されるようになりました。
指標がバリューチェーン全体に広がることが予想されるため、これを機にチェックすることをお勧めいたします。
森林
森林質問書は統合対象となりますが、土地利用の変化や商品作物ごとの依存度、2023年より強化されたランドスケープや管理区域に関する投資や行動に関する質問は、2024年のスコアレポートでも使われることが想定されます。
またCDPでは今後、DCF(Deforestation and Conversion Free:森林伐採や自然生態系の転換の撲滅)のボリュームについての質問を増やしていく方針を示しています。
従来は森林伐採に争点が当たることが多かったですが、今後は自然生態系の転換に関する質問も増えることが想定されるため、絶滅危惧種の保護や里山やマングローブなど自然生態系が豊かな場所の保全活動などに関わっている場合は、高スコアを見込める可能性があることを頭に入れておくといいでしょう。
CDP2025に関するQ&A
CDP2025スコア回答の締め切りを教えてください。
2025年の回答提出締め切りは9月15日週とアナウンスされています。
CDPに昨年初めて回答しました。振り返りを行いたいのですが、適切な方法を教えていただけますか。
ガイドラインやスコアリング基準と照らしてみて失点可能性があるところを確認いただくことが良いかと考えています。
弊社でも模擬採点は可能ですのでもしご興味ございましたらご用命いただけましたら幸いです。⇒お問合せフォーム
まとめ
質問項目の統合やIFRS S2基準の評価方法の導入など、CDPスコアレポートの枠組みは2024年より大きく変更されます。より厳格、かつ幅広い範囲を答える必要が出てくるため、自社のサステナビリティ活動について熟慮した上で、具体的に記載することが重要です。
#CDP #2024
CDP(気候変動質問書)とは?
【このホワイトペーパーに含まれる内容】
・CDPの概要やその取り組みについて説明
・気候変動質問書の基本情報や回答するメリット、デメリットを詳細に解説
・気候変動質問書のスコアリング基準と回答スケジュールについてわかりやすく解説

参考文献
[1] CDPジャパン「CDP気候変動レポート2023:日本版」p14
[2] CDPジャパン 「CDP気候変動レポート2022:日本版」p13
[3] CDPジャパン「スコアレポート解説資料」
[4] CDP「Corporate Disclosure Framework Key Changes for 2024 」
[5] IFRS「ISSB at COP27: CDP to incorporate ISSB Climate-related Disclosures Standard into global environmental disclosure platform」
[6] 大和総研「ISSB の「IFRS S2」(気候関連開示)の具体的な内容」
[7] CDPジャパン「2023年 CDP気候変動質問書 回答に向けて(詳細版) ver. 1」
リクロマの支援について
弊社はISSB(TCFD)開示、Scope1,2,3算定・削減、CDP回答、CFP算定、研修事業等を行っています。
お客様に合わせた柔軟性の高いご支援形態で、直近2年間の総合満足度は94%以上となっております。
貴社ロードマップ作成からスポット対応まで、次年度内製化へ向けたサービス設計を駆使し、幅広くご提案差し上げております。
課題に合わせた情報提供、サービス内容のご説明やお見積り依頼も随時受け付けておりますので、お気軽にご相談ください。
⇒お問合せフォーム
メールマガジン登録
担当者様が押さえるべき最新動向が分かるニュース記事や、
深く理解しておきたいトピックを解説するコラム記事を定期的にお届けします。